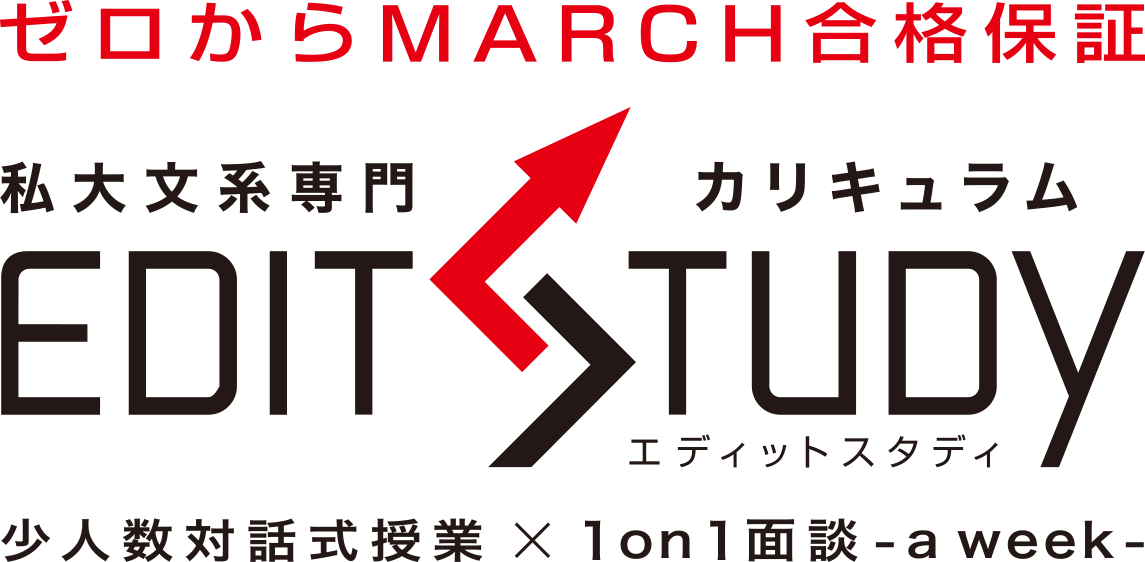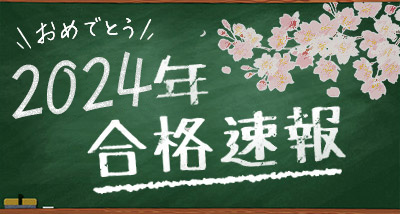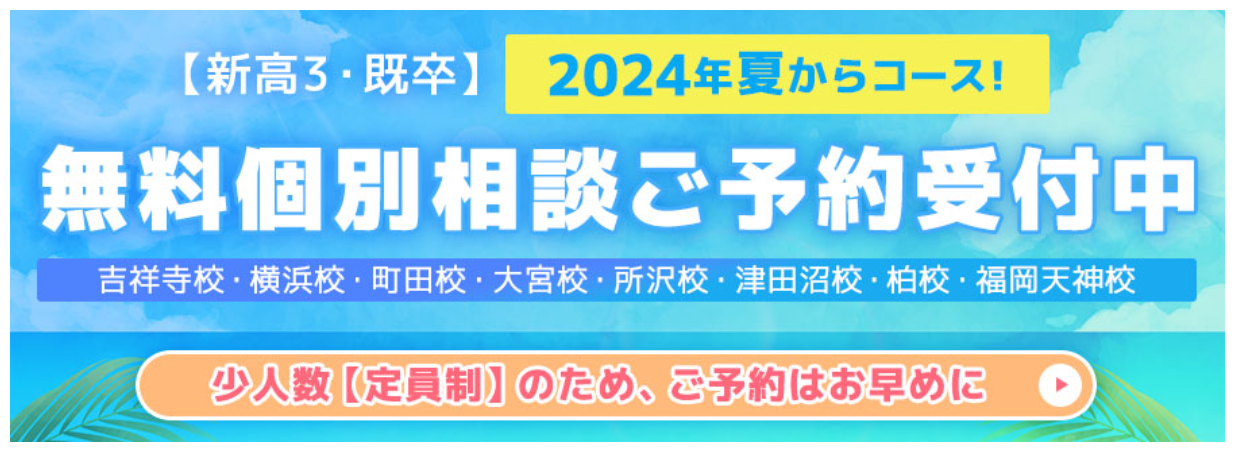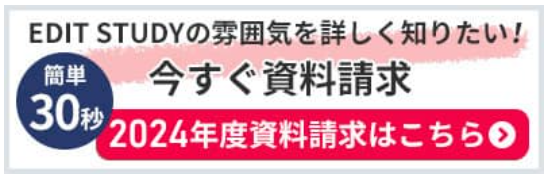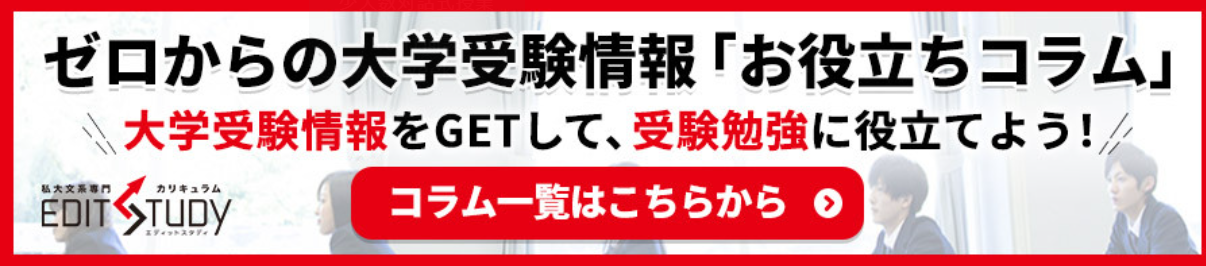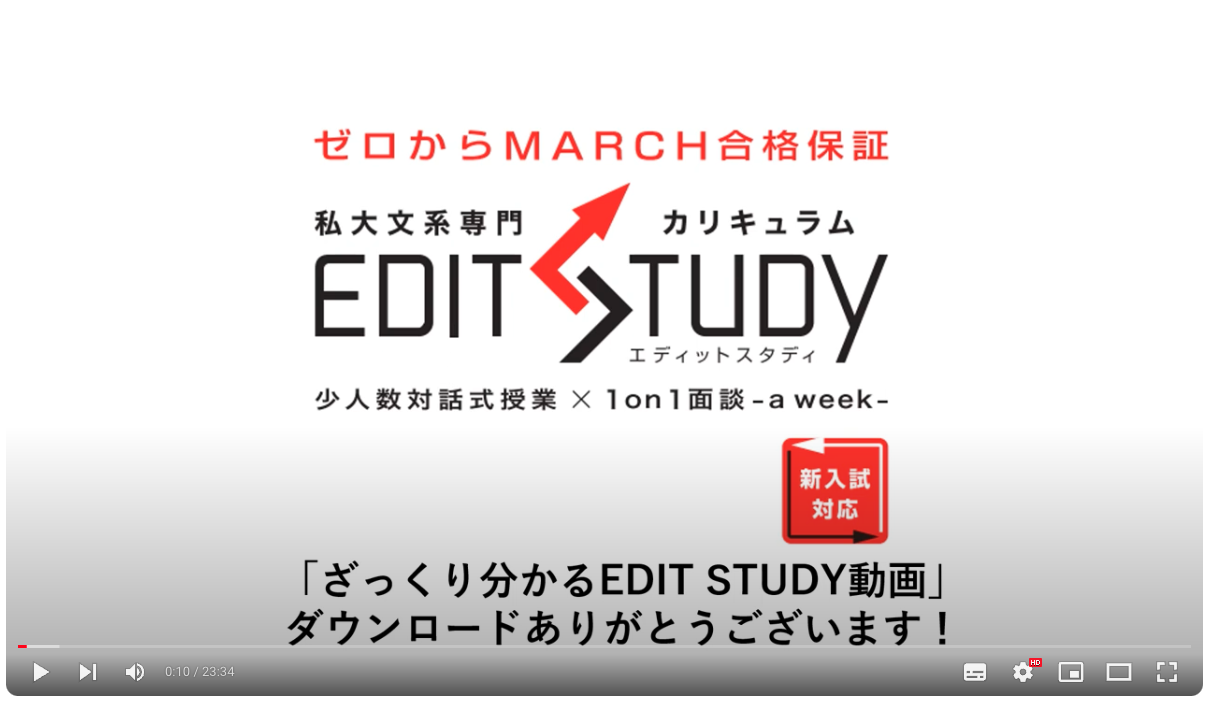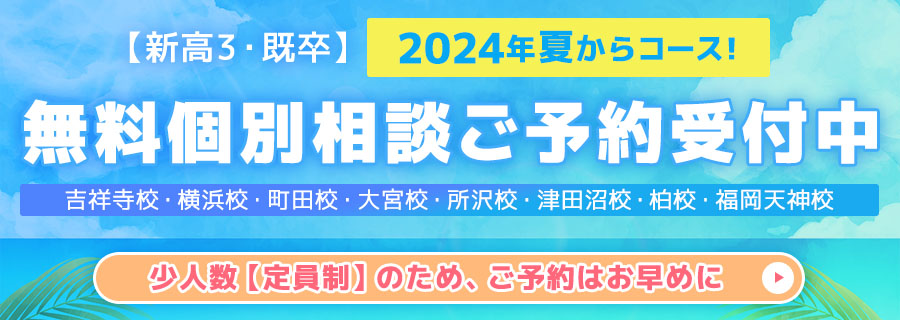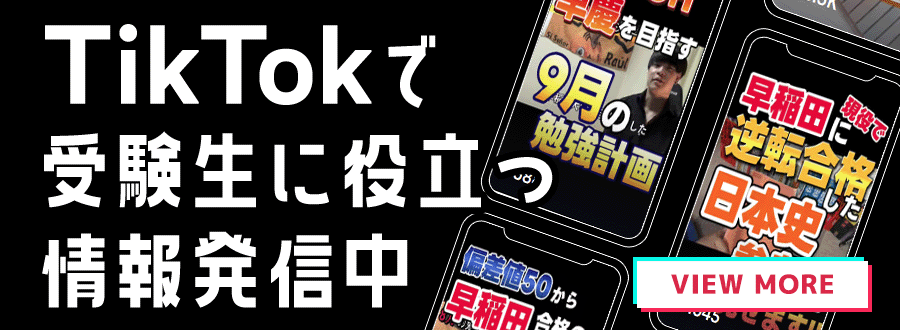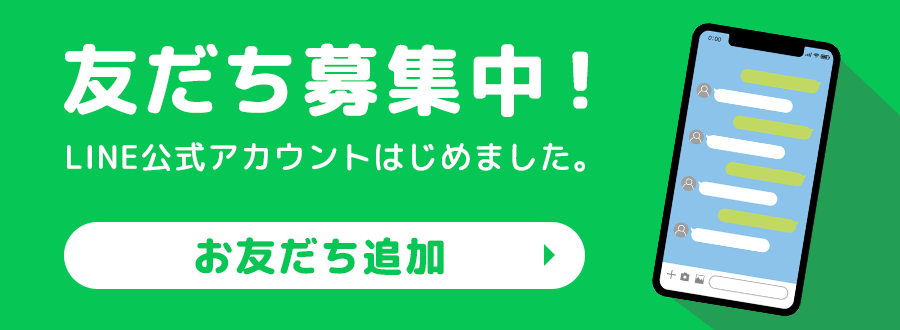2022.11.7
塾と予備校の違いとは?
Table of Contents
こんにちは。EDIT STUDYです。今回の記事では「塾と予備校の違いとは?」というテーマでお話していきたいと思います。弊塾も大学受験に取り組む高校3年生と既卒生を対象として首都圏を中心に校舎を展開していますが、大学受験だけでなく塾や予備校は世の中に沢山あります。しかし、その中で塾と予備校の違いについて明確に理解できている方は決して多くはないかと存じます。まずはその定義から見ていきましょう。
そもそも呼び名の違いは何故あるのか?
塾と予備校・・・・そもそもなぜこうした呼び名の違いはあるのでしょうか。まずこの疑問にお答えするために、塾と予備校それぞれの言葉の定義から見ていきましょう。
塾と予備校の定義
塾
塾を辞書で調べると「年少者に学問・技芸を教える私設の小規模な学舎。勉学する生徒の寄宿舎。」と出てきたりします。つまり、目的に限られず、勉強を教えてもらう場所のことを指します。塾は広く「勉強する場所」という意味になるということです。
予備校
次に予備校も辞書で調べてみると「上級の学校、特に大学への進学希望者に、入学試験準備のための教育をする各種学校。」などと表現されています。つまり、大学受験や資格試験などなにかに合格することを目的として通う「予備学校」、つまり受験生に向けた勉強場所のことを指し、受験などある目標への合格を目的にした塾が「予備校」になります。塾のカテゴリの中に予備校があるイメージです。
歴史
次に塾と予備校を取り巻く歴史を見ていきましょう。そもそも塾の枠組みの中で、予備校という言葉一般化されたのにはどのような歴史があったのでしょうか。もともとは高度経済成長期頃から大学受験の大衆化により、数年のうちに予備校は急速に発展するようになっていきました。
この時期にいわゆる3大予備校である、駿台予備校・河合塾・代々木ゼミナールが1950年代の中盤から後半にかけて、急成長する下地が形成されました。
そして1960年代から1970年代にかけて、都立学校群制度や共通一次試験が成立したことが追い風となり、予備校は成長期を迎えます。1970年代、1980年代、1990年代前半のいわゆる受験バブルの時代においては、現役での進学のほかに高校浪人、大学浪人などで高校進学や大学進学することも一般化していきました。
当時は「一浪」で「人並み(ひとなみ)」などと俗に言われた時代でもありました。それくらい、浪人が一般的であった時代でした。そのため独自の予備校文化も形成されるに至りました。こうした時代背景もあり、今よりも圧倒的に浪人生が多く、高校と大学の間の存在、そして大学の講義に近い形式の予備校というものが形成されました。
つまりまとめると、高校と大学の間の存在、そして大学の講義に近い集団授業形式のものを”予備校”と呼び、大まかにそれ以外を”塾”とまとめると分かりやすいでしょう。
塾と予備校それぞれの特徴
塾の特徴
前述した通り、予備校に比べて比較的対象の生徒が年少者であったり、大学受験に限らず学ぶ環境というイメージが強いですが、具体的にどのような特徴があるのでしょうか。予備校に比べてまずは1クラスの人数が少ないという特徴が挙げられます。
大学受験においても個別指導スタイルは予備校とは呼ばず、個別指導”塾”と呼んだりしますが、スポーツや習い事でも1:1や1:2など個別レッスンや少人数で教わるところは多くの場合、塾と呼ばれます。なので特徴の2つ目としては塾で教える講師は大学生のアルバイトであることも多々あります。
これは生徒1人ひとりに対して寄り添える環境を提供するため、講師の数も多く確保する必要があるため必然的に人材確保の観点でも大学生のアルバイトが登用されるのは想像に難くないでしょう。その分3つ目の特徴としては予備校に比べて、生徒一人ひとりに寄り添った指導をしてくれるというのは”塾”の特徴の一つでもあるでしょう。
ただしその分、予備校に比べて費用面が”塾”特に個別指導塾の場合はかさんでしまうことも想像に難くないかと思います。(講師1人につき生徒1人のため、単純に費用が上がってしまいます。)実際に大手予備校の場合は、高校生の年間にかかる費用は50万前後(季節講習もあるので、これに+αかかりますので、70-100万前後)になりますが、個別指導塾の場合はベースで70万前後、これに成績に合わせて季節講習や増コマといった形で追加費用が掛かってきますので、最終的に100万円を超えるケースも少なくありません。
向いている生徒
基本的に大学受験と個別指導の相性はよくありません。ただし「偏差値60以上の得意科目が2教科ある場合」有効に機能するかもしれません。 例えば帰国子女で英語は偏差値70以上、暗記を頑張ってきた社会は偏差値60、海外での生活が長く、国語だけは偏差値48、というようなケースです。
個別指導の良いところは生徒ひとり一人の学力・事情を考慮して指導してくれる部分でして、上記の生徒がGMARCH合格を確実にするためには、国語の偏差値を2上げれば良いので(3教科平均偏差値60となる)生徒のペースに合わせても受験には間に合うという訳です。
衛星予備校で国語のみ受講しても良いのですが、1科目だけ極端に偏差値が低いというのは個人的な事情がある可能性が高く、一方通行の動画を視聴するというよりは、寄り添って教えてくれる先生が傍にいた方が、成績向上に繋がるはずです。
予備校の特徴
”塾”に比べての”予備校”の特徴としては、何といっても人気講師による質の高い授業でしょう。それこそテレビに出ているような林修先生や安河内哲也先生のような人気講師の授業をLIVE授業で受けられることが特徴の一つとして挙げられます。
その分2つ目の特徴としては大人数での授業というのが挙げられるでしょう。校舎や講義によっては100-150人、200人授業など大学の大教室での講義形式のような授業もあったりします。これがまさに大学受験の”予備校”の特徴でしょう。
向いている生徒
前述した予備校の特徴の1つ目の人気講師による質の高い授業、そして大人数授業ということで、塾に比べると生徒との距離感は少し離れており、基礎学力がないと付いていけないという点があります。ですので基本的に予備校に向いている生徒としては基礎学力が備わっている生徒になります。これはなぜなら、人気講師による質の高い授業なので内容は大学受験の難関大で出題されるような問題のレベルを授業では扱いますので、想像に難くないかと思います。
※上記が理由で予備校の授業は『予習前提』で進みます。つまり基礎が分かっている前提で授業が進むわけです。実際に授業では大学の過去問の解説などを実施しますので、基礎が分かっていなければついていけなくなります。
また1つの授業で100-200人生徒が居ますので、質問はおろか相談等は授業を担当している講師にはほとんどできません。なので予備校では自己管理能力が求められるというのは”塾”の特徴との違いで挙げられると思います。予習や復習のスケジュール、科目の優先順位なども全て自分で管理する必要があります。実際に高校を想像すれば30-40人1クラスだと思いますが、担任の先生が全ての生徒の全ての科目の学習スケジュールを管理しているかどうかを考えればこれも理解できるはずです。
質問や相談対応も基本的に授業を担当していない、生徒の成績を模試でしか把握できていない大学生のアルバイトのチューターが対応します。ということは生徒の得手不得手を把握できていませんし、どれだけ理解できているかも把握できていません。しかも大学生のアルバイトなので自身の成功体験しか共有できるものはないので、出身高校の偏差値や部活動に入っているかどうか、いつから通塾し始めたか、そもそものスタート時点の学力など、全てが合致しなければ、汎用性の高いアドバイスにはなり得ません。
ですので予備校形式に向いている生徒は基礎学力や自己管理能力が高く、計画的に予習ができ、自身の苦手を把握し計画的に復習のスケジュールを立てることができる生徒になってきます。
まとめ
さてこのように塾と予備校の違いは何なのか?というテーマで、それぞれの言葉の定義から始まり、順を追って歴史を紐解きながら違いを確認してきました。では最終的に塾と予備校の違いを理解した上でどうすれば良いのでしょうか。現在では大手予備校以外にも様々な学習形態の塾や予備校が乱立し、どこで塾と予備校を線引きすれば良いのか、そういった点も難しくなってきました。
◆主な講義形式
・集団授業
・少人数
・個別指導
・映像授業
・AI
・自学自習
結局重要なのは、自分自身の学力と目標とする志望校、そしてそれらに対し、講義形式やサポート体制を吟味した上で自身の成績を最大化する上で最適だと思う環境をきちんと選べるかどうかです。最後に下記にお役立ちできそうなコラムのリンクを貼っておきますので、ご興味のある方は是非続けてご覧ください。
大学受験塾・予備校「ホントに正しい」選び方
※来年の受験を控えた方必見!下記バナーをクリックしてください!
参加受付開始!先着順なのでご予約はお早めに!
※各大学グループで特集を組んでありますので、興味がある方は下記↓をクリックして下さい。