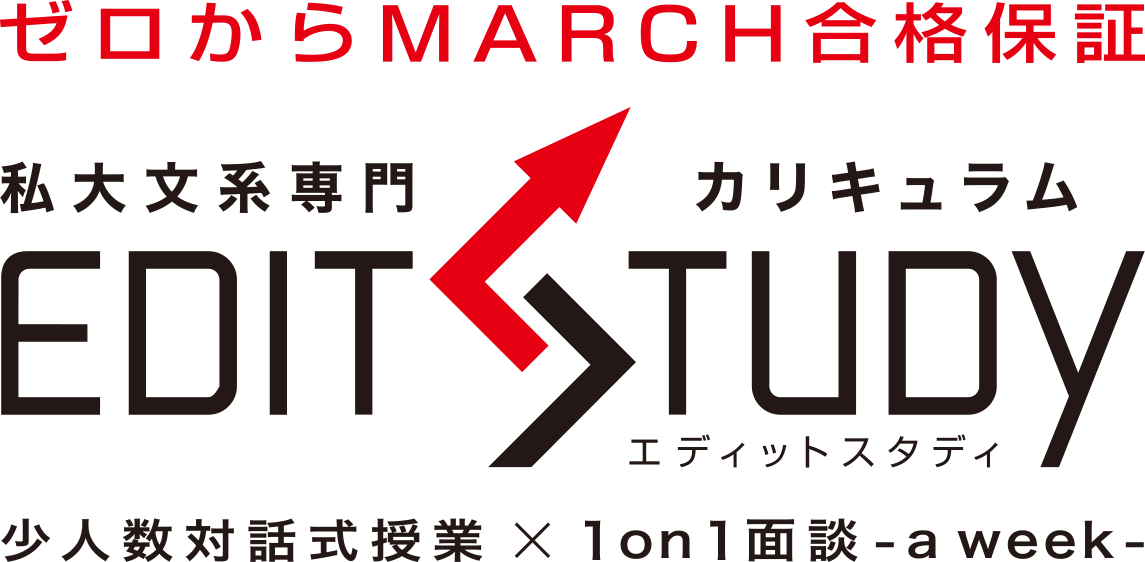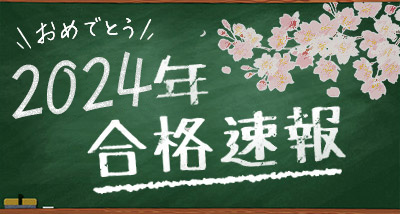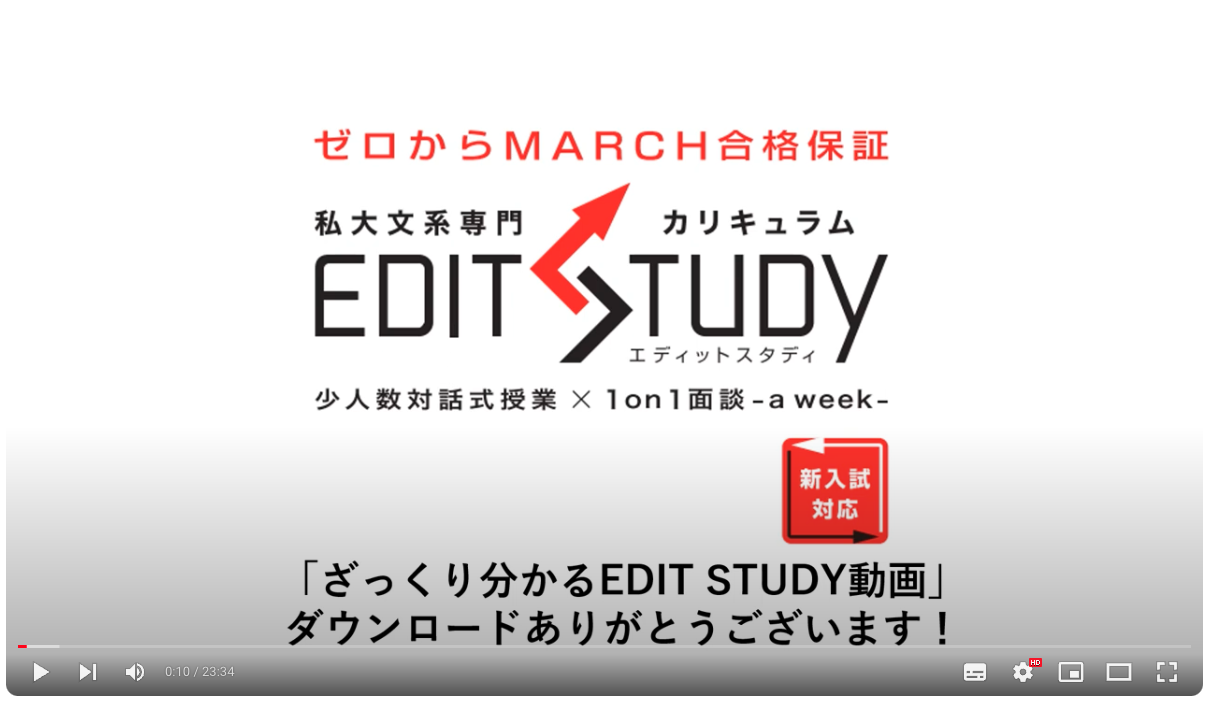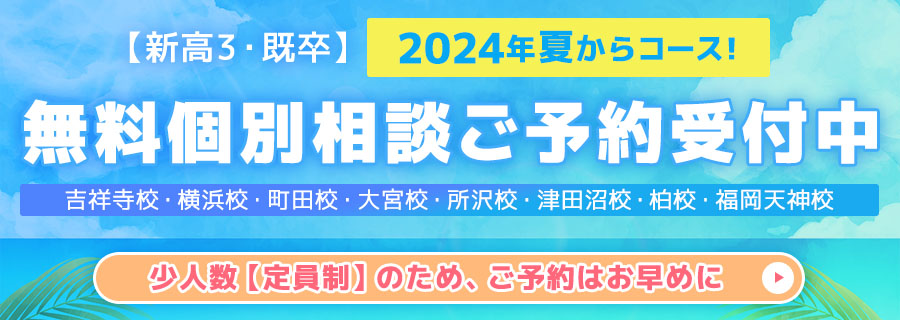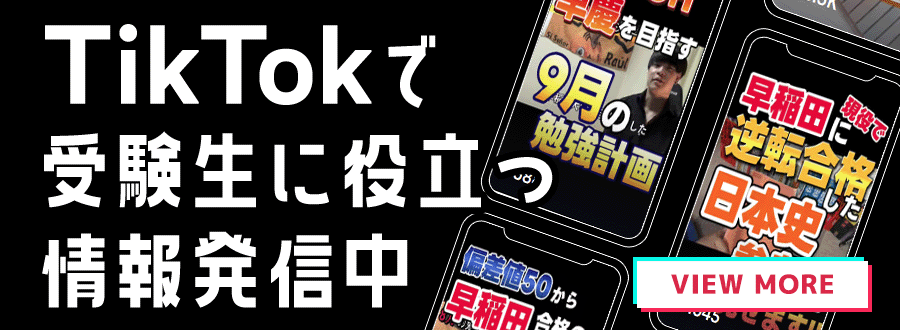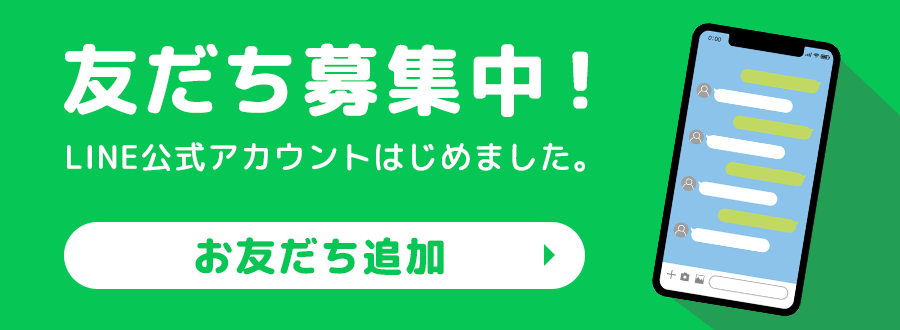2019.9.16
<2019年10月更新>【新入試現代文-第三問-】プレテスト分析&対策
Table of Contents
みなさんこんにちは。2021年度大学入試改革(新入試)担当の初田です。
今回はH30年第二回試行調査国語の第三問についてみていきます。
TOPICS
従来のセンター試験小説とは異なる出題傾向
共通テスト現代文について
従来のセンター試験小説とは異なる出題傾向
✓出題傾向のポイント
✓必ずしも小説が出題されるわけではない
✓評論の解き方が流用できる
過去二回行われた試行調査ではそれぞれ、小説とそのあらすじ、エッセイと同一作者の詩が問題文として出題されました。二度の試行調査を合わせ考えると、本番の共通テスト第三問では、文芸に関わる様々な題材の文章から、それに関連する複数のテキストにまたがった出題がされることが考えられます。よって、共通テストでは必ずしも従来の小説型の問題が出題されるとは限らず、登場人物の心情を問う問題がなくなることも予想されます。そのため、本文の心情表現を緻密に追って解答を導き出すという従来の方法が使えなくなるかもしれません。しかし語句の意味や表現方法に関する説明は従来のセンター試験と同様の出題であり、国語に関する知識を問う問題は引き続き出題される可能性が高いです。
設問の質としては、他の大問と同様、本文の内容を抽象化または具体化し、選択肢と照らし合わせるという共通テスト全体の方針に沿った出題となっていました。このことから、従来のセンター試験評論のように、本文と選択肢の緻密な解釈を行い解答を導き出す解き方が流用出来そうです。
共通テスト現代文について
✓共通テストが図りたいのは思考力・判断力・表現力
✓従来のセンター試験のやり方は勿論流用できる
共通テストがこの度の改革で受験生の能力の何を新たに評価したいのかというと、受験生の持つ思考力・判断力・表現力の三つの能力となります。試行調査を解いていく中で、過去出題されたすべての問題が複数の文章や図表で構成されていることから、論旨の理解や情報の抽出、抽象化、そして具体化行い解答を選択することが必要であると感じました。
全体を通してみると、従来のセンター試験のような緻密な本文と選択肢の解釈に加え、問題文が伝えたいことは何か(情報の抽出)、それに基づいて類例などを考え(情報の具体化)、記述あるいは適切な選択肢を選ぶ(判断・表現)という応用的な対応が必要になるでしょう。しかしながら、問題が極端に難化しているわけではなく、新たな対策を取ることで高得点を安定させることができるでしょう。
落ち着いて情報を集め、対策に取り組んでいきましょう。
EDIT STUDYでは2021年度大学入試改革(新入試)に向けカリキュラムの作成を行っています。
共通テストに合わせた学習ページも用意されますので、是非弊塾HPをのぞきにきてくださいね。
新大学入試に向けたDIETSTUDYの取り組み
新大学入試に向けてDIETSTUDYが取り組んでいることを
分かりやすく1分で理解できるようにまとめました。