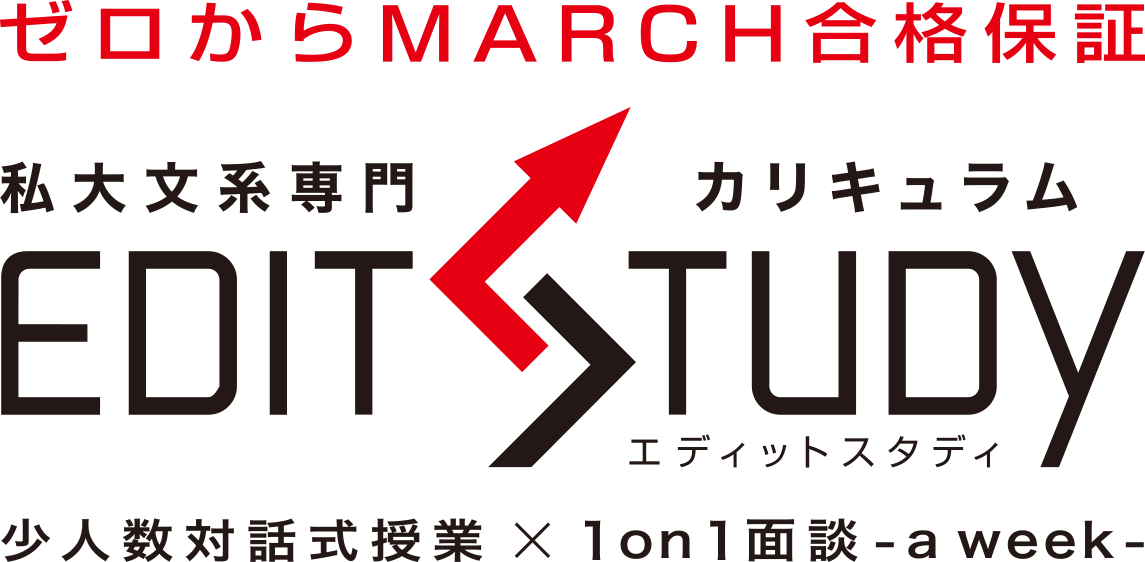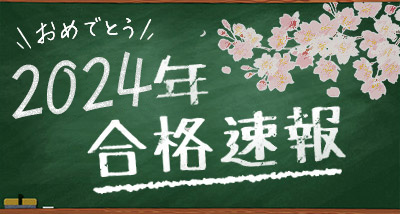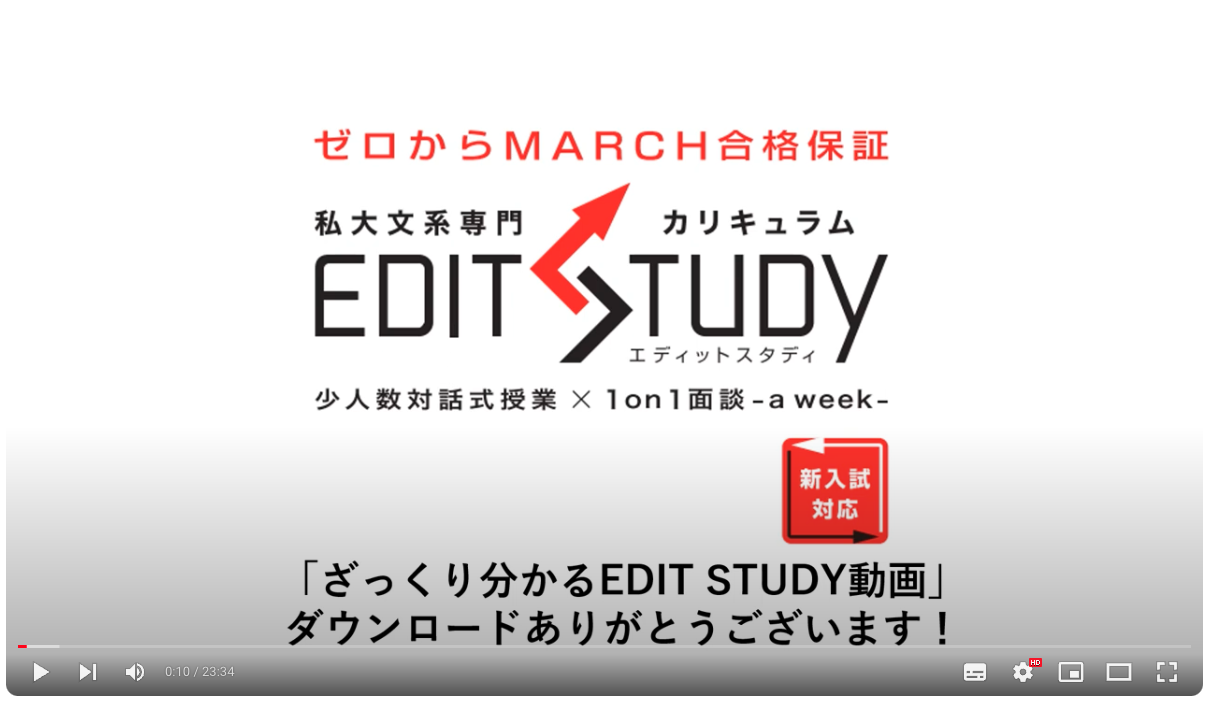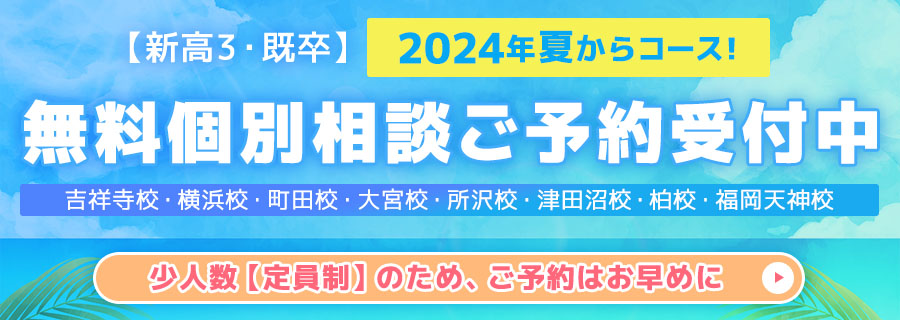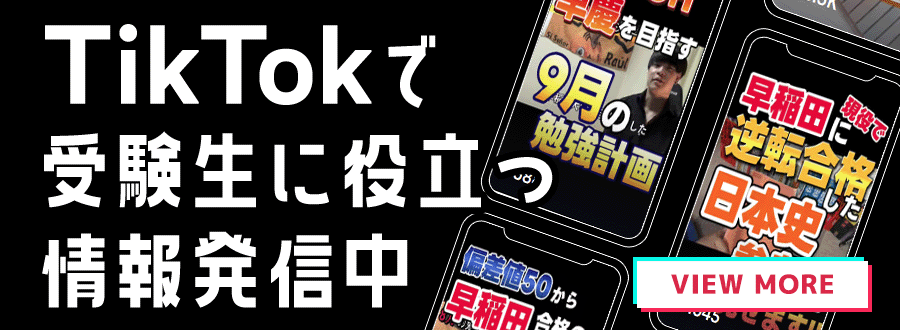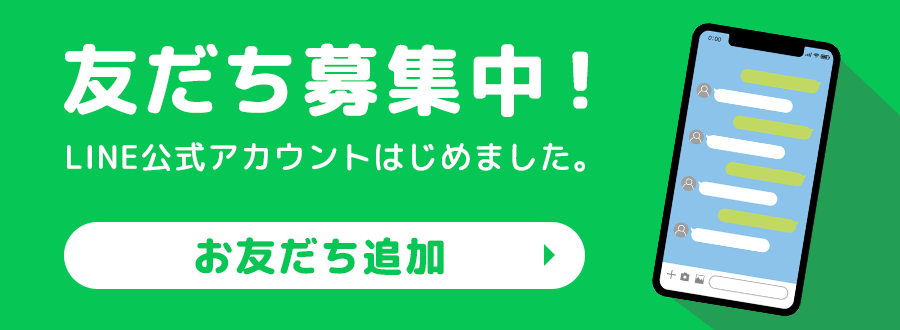2020.8.28
【2020年8月更新】2021年度大学入学共通テスト!英語はどう変わるの?~リスニング編~
Table of Contents
今回は2021年度新入試から導入される「共通テスト」が従来の「センター試験」からどのように変わるのか?に関して見ていきたいと思います。科目ごとで特性も違うので今回は私大文系で配点の高い「英語」に関して見ていきたいと思います。他のコラムで英語の次に変わると言われている「国語」に関しても見ていきますので、国語が気になる方はそちらもご覧ください。今回の記事は2020年8月時点の文科省等の発表を参考に作成しています。
共通テストで「英語」はどう変わるのか?
新入試ということで旧センター試験から共通テストに移行します。前回はその中でも特にリーディングに関してお話ししました。今回は第2弾ということでリスニングになります。第1弾のリーディングと同じように下記3点を軸にお話していきます。
①2021年度共通テスト配点
②2021年度共通テストリスニング問題構成&試験内容
③2021年度共通テストリスニング対策
①2021年度共通テストリスニング配点
わかりやすく2020年センター英語と比較していきます。
共通テストは発表されている内容と試行調査を参考にしています。
≪old≫
・2020年センター試験
リーディング 200点
リスニング 50点
合計 250点(圧縮して200点換算)
≪new≫
・共通テスト(発表&試行テスト参考)
リーディング 100点
リスニング 100点
合計 200点
ここで重要なのは前回お話したように各大学が大学ごとで共通テスト利用の際のリーディングとリスニングの配点を設定しているということです。なので慌てる前に志望校の試験要綱を確認しましょう。
②2021年度共通テストリスニング問題構成&試験内容
☆問題構成
≪old≫
・2020年センター試験
→大問構成は4問
大問1:対話文 イラスト&語句選択問題
大問2:対話文 応答文選択問題
大問3:対話文 質問に対する回答選択問題
大問4:体験談&対話文 質問に対する回答選択問題
≪new≫
・共通テスト(試行テスト参考)
→大問構成は6問
大問1:対話文 内容一致&イラスト選択問題
大問2:対話文 イラスト選択問題
大問3:対話文 質問に対する回答選択問題
大問4:A図表&分類・並び替え問題 B状況・条件判断問題(1回読み)
大問5:要点把握&図表読み取り問題(1回読み)
大問6:議論(ディベート)意見要約&判断問題(1回読み)
※ただし設問数が大幅に増えたわけではありません。
大問や設問の構成以上に内容部分で変更がありますので、そちらに関して見ていきましょう。
☆試験内容
≪old≫
・2020年センター試験
→音源の再生は2回
≪new≫
・共通テスト(発表&試行テスト参考)
→音源再生は1回と2回の混在
→大問3までは旧センター試験と近い内容
→4.5.6は今までにない出題傾向
→事前の対策、問題傾向の把握は必要
③2021年度共通テストリスニング対策
ここでは2でお話した問題構成や試験内容が旧センター試験から変更点があり、受験生に求められる要素や準備に関して以下3つのポイントで簡単にお話しておきます。
英語耳
共通テストのリーティングの語数も旧センター試験が4000語前後に対し、試行調査では約5400語前後になっていました。リスニングでも旧センター試験が約1100語に対し試行調査では1500語になっていました。「量が増え」「速度が速くなる」(試験時間は一緒のため)「1回しか読まれない」ことから分かるように英語を聞き取る力、いわゆる「英語耳」が必要です。普段から英語に聞きなれていると養われる力になるので、どれだけ英語の音声に触れているかが大事です。
全体把握と要約する力
旧センター試験にはなかった、全体や状況・条件を把握して解答を選ぶ形式や、全体を把握し、要点をまとめた上で解答を選ぶ形式、流れてくる英文の議論を聞いて意見を要約して解答を選ぶ形式など全体を把握し要約する力が求められます。これは段階を踏んで対策することが出来ます。まずは全体を把握できる「英語耳」を養います。上述したようにとにかく英語に聞きなれることが重要です。次に聞いた英文の要約、つまり「まとめるとこの文章はこういうことだ」とまとめる練習をすることです。
問題形式と解答作業の事前準備
共通テストの試行調査通りの出題形式であれば、大問4以降の特に大問5.6に関しては英文が1回読みの上、英文を聞き取りながらメモや図表を完成させたうえで必要な情報と聞き取った内容を照らし合わせて解答する必要があります。しかし、初見ですとそもそも何を聞き取ればよいのか?どんなメモや図表の情報を埋めれば良いのかわからないまま1回読みの英文が終了してしまいます。そこで対策として、各大問の出題形式に合わせて全体を把握しながら、どんな情報をどんな形式で抜き取れば良いかのトレーニングがオススメです。特に大問ごとに反復練習がオススメです。
※実は第1弾で紹介したEDIT STUDYの「速読読込み」という勉強法は「英語耳」と「全体把握と要約する力」を養ううってつけの方法でもあります。気になった方は是非第1弾もご覧ください。