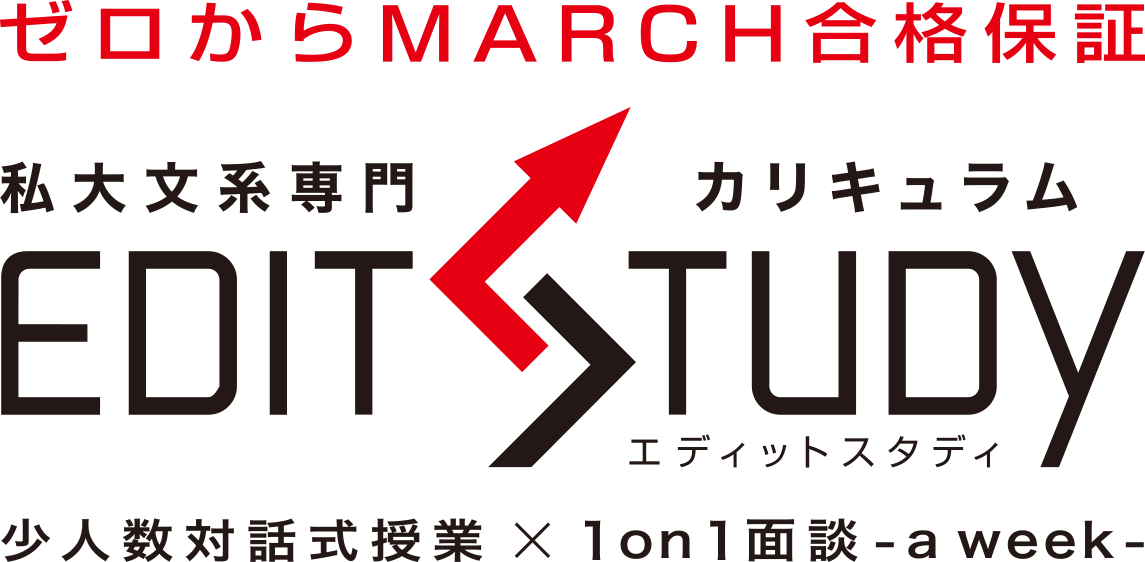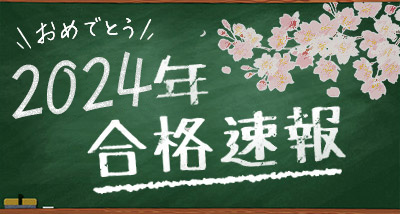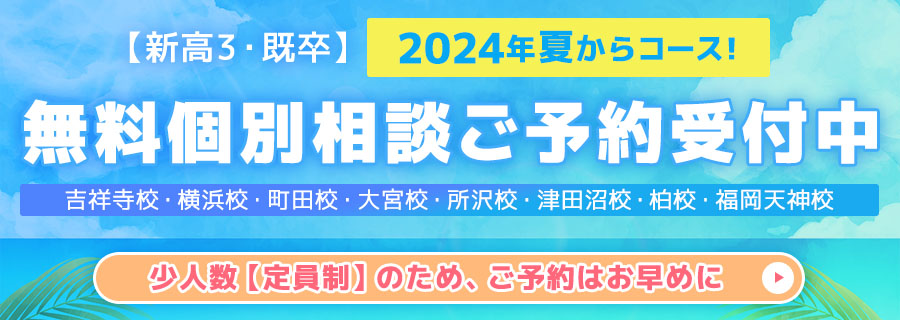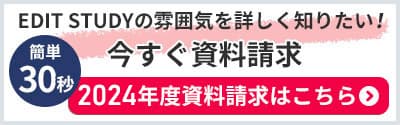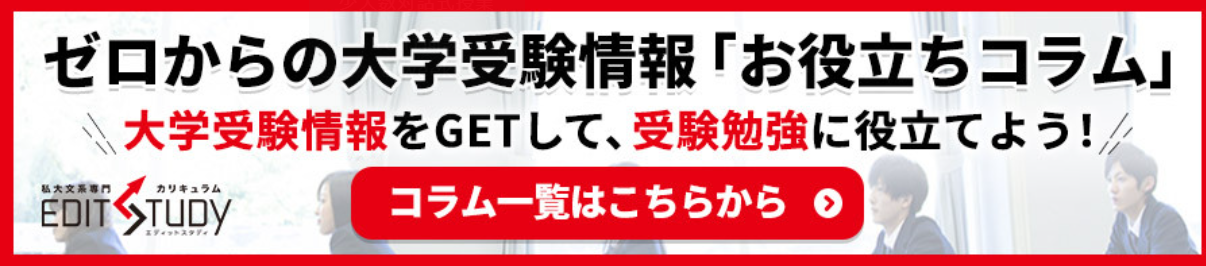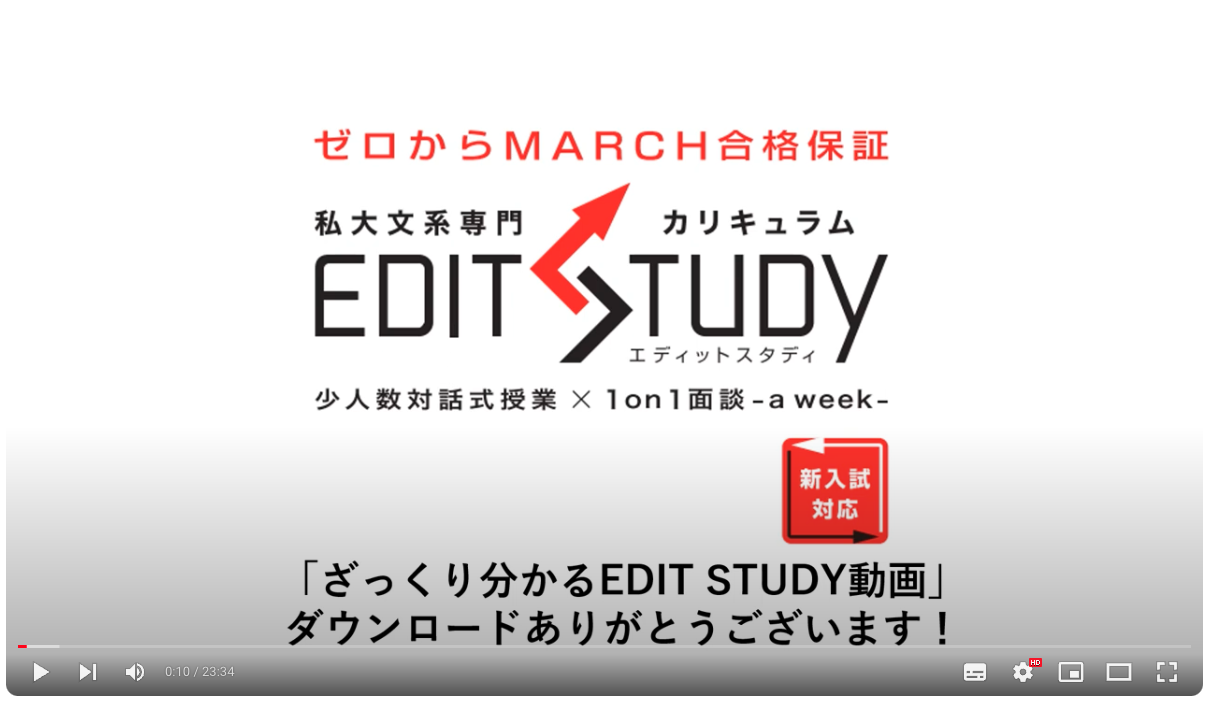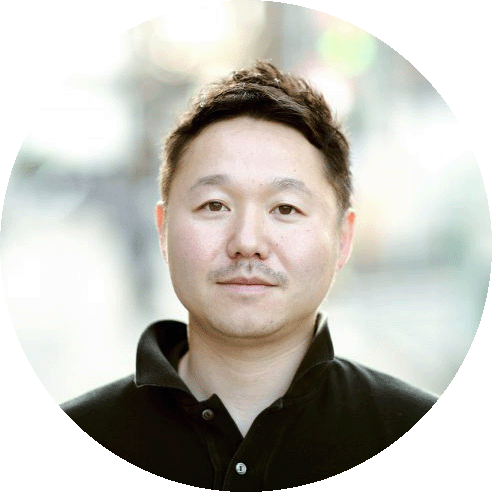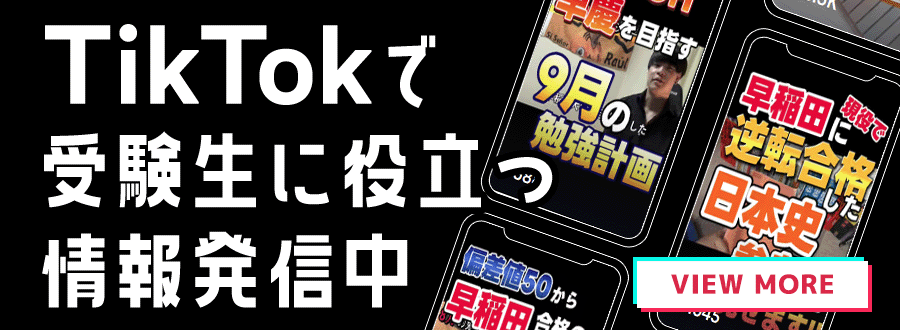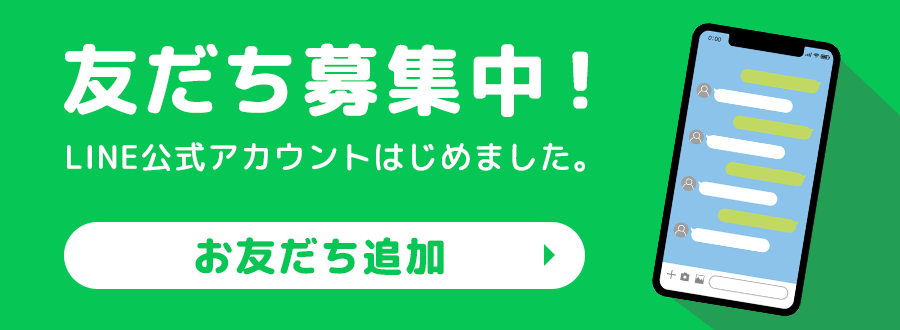2019.7.22
<2019年8月更新>「GTEC」「IELTS」受験はどうなの!?
Table of Contents
2019年11月1日、文科省は大学入試での英語民間試験の来年度導入を延期することを表明しました。
以下大学・学部情報は2019年10月時点のコラムになりますので、導入延期を踏まえた新たな情報は各大学・学部のHPをご確認下さい。本コラムでも順次情報を更新していきますので、引き続き本コラムをよろしくお願いします。
以下2019年10月時点コラム——————————————
こんにちは、2021年度大学入試改革(新入試)担当の初田です。
前回はケンブリッジ英検と英検を見ていきました。
引き続き、2021年度大学入試改革(新入試)に向けた残りの□試験について確認していきましょう。
今回はGTECとIELTSについてです。
GTEC
GTECは株式会社ベネッセコーポレーションが運営するスコア型英語能力試験です。4技能試験のうち日本国内の民間企業が運営主体でありかつ試験の運営主体が教育事業も一括して行う唯一の試験です。
試験はCore/Basic/Advanced/CBTに分けられており、それぞれの試験でCEFRのスコア上限が定められています。
英検と異なり、一番下のレベルであるCoreからライティング、スピーキングが課せられています。(英検は3級から)
問題の難易度が日本国内の学校教育に準拠しているため、自分の学年に合った試験を受けることができ、その意味では英検を除くほかの試験よりなじみやすいでしょう。
20年度の実施日は6月14日、7月19日、10月4日、11月1日の四回となっておりますが、今年5月の段階で会場などの具体的な実施場所については未定のようです。
◎対応しているCEFRレベル:A1~C1
◇受験上のメリット
全ての4技能試験の中で唯一、試験実施主体が自前の教育事業を行っていることが何よりのメリットとなります。学習と試験を同じグループで行うことができるため、ベネッセが運営している学習塾での学習が直接GTECの得点に結びつきます。
◆受験上のデメリット
GTECの学習をするのであればベネッセの運営する学習塾に行くことが最も効率的です。そのため、ベネッセの運営する学習塾が近くにない、あるいは学習スタイルが合わず通わないのであれば、GTECを受験するメリットはさほどありません。その場合は英検受験も考慮に入れ自分に合った学習方法を検討するべきでしょう。
また、受験上のメリットを享受してGTECを受験するのであれば学習は全てベネッセに委託する形になります。その為授業料をベネッセに支払い続ける必要があるため、年間にかかる学習費用が大きくなる可能性があります。
ベネッセの運営する学習塾で成績が上がっており、金銭的に問題がないのでなければ英検受験をまずは考えるべきでしょう。
IELTS
IELTSは海外留学や研修のための英語力証明や、イギリス、オーストラリア、カナダなどへ海外移住申請に必要とされる英語能力テストです。国内における実施は複数の組織が共同で担っており、その中には日本英語検定協会も含まれています。
テスト結果は1.0から9.0まで0.5刻みのバンドスコアで示され、合格、不合格はありません。各パートごとにバンドスコアで示される他、総合評価としてオーバーオール・バンドスコアが与えられます。
試験の種類は「アカデミック・モジュール」と「ジェネラル・トレーニング・モジュール」の二つがあり、アカデミック・モジュールは、英語で授業を行う大学や大学院に入学できるレベルに達しているかどうかを評価するもので、ジェネラル・トレーニング・モジュール
は英語圏で学業以外の研修を考えている方やカナダなどの旧英国領の国々に移住申請をされる方を対象とした英語能力評価を行うものです。
実施は、札幌、仙台、埼玉、東京、横浜、長野(松本/長野)、金沢、静岡、名古屋、京都、大阪、神戸、岡山、広島、山口、福岡、熊本、沖縄と比較的多くの場所で行われます。
なお、山口・沖縄を除く実施は日本英語検定協会、山口、沖縄での実施は北九州予備校が実施していますので、都合の良い場所を選択してください。
◎対応しているCEFRレベル:B1~C2
◇受験上のメリット
ありません。英語になじみのない日本生まれ日本育ちの学生は受験を検討するべきではありません。
◆受験上のデメリット
そもそも2つの試験の目的が、日本語で授業を行う大学に進学することを希望している受験生を意識したものになっていません。またCEFRレベルも下限のスコアが4.0=B1(英検2級~準1級程度)となっていることから、語彙や文法も難易度が高く、国内の学校や塾・予備校で学ぶ内容をあまり流用できません。
新大学入試に向けたDIETSTUDYの取り組み
新大学入試に向けてDIETSTUDYが取り組んでいることを
分かりやすく1分で理解できるようにまとめました。